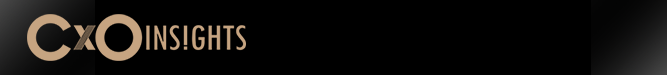
開発費用と工数は半分 2人でやっていたことが1人でできるように
生成AIを活用しやすくするシステムさえ構築できれば、企業の生産性は著しく上がる。具体的にどんなことができるようになるかを聞くと、まずは「時間の節約」だという。喜多社長は「例えば、ある製造業の会社が、過去に開発したAという技術に関する特許を参照したいとします。ただ実は、過去の情報を探すのは意外に大変なのです。しかしRAGが実装できれば、それが簡単に見つかります」と胸を張る。他の使い方もあるという。
「ある技術をベースに、新たな『製品B』を開発するにあたり『必要とされる要素技術は何ですか?』という質問が可能です。『こうした方がいいんじゃないか?』というようなアドバイスももらえます。助言するのは、生成AIの強みです」
一般的に日本の経営層はITのリテラシーが低いと言われがちだ。生成AI×RAGの良さを彼らに知ってもらう必要がある。
喜多社長は「今、私たちのソフトウェア開発の現場は、GitHub Copilot(コーディング中にAIがコードのプログラマーに対して提案をしてくれる機能)を使っています。エンジニアに『感覚的な数値で工数はどのくらい減ったのか?』を尋ねると、25~50%と言うんです。実に半減しています」と驚きの回答をする。
「RAGが入ることによって、実行できることが増え、かつ精度も上がる。これがRAGの強みです。工数が半分になるという意味は、2人でやっていたことが1人でもできるようになることです。単純に10億円かかっていた開発費用なら、5億円になるという話なのです。これは劇的な変化だと思います」
LLMを開発するよりRAGを導入したほうが効率的
具体的にどの業界にこのシステムは向いているのだろうか。村田エグゼクティブマネージャーは「いくつかのパターンの想定ができています。現在の生成AIでは、公開されている情報をベースにしていますから、逆に公開情報が少ない業界に向いているともいえるかもしれません。例えば、外に出せない情報を多く持っている製造業、金融、証券などはRAGの利用価値が高いと考えています」と話す。

